二者択一話法 とは
二者択一話法とは、二者択一で相手に選ばせる話法のことです。たとえば、「AとB、どちらがよろしいですか?」のような二択の質問をすることで、決定権を相手にゆだねながら、相手に選ばせる方法です。
アメリカの催眠療法者・心理学者のミルトン・H・エリクソンが提唱したため、エリクソニアン・ダブルバインドとも呼ばれます。
二者択一話法 使用例
二者択一話法は営業で相手に契約させるテクニックとして有名な話術です。
営業の話法として有名
二者択一話法は、AかBかのどちらかを選ばせる話法です。
たとえば、車を売りたいときに「この車を買いますか?」と質問すると、「買う」か「買わないか」の二者択一になるので、顧客は「買わない」選択肢を取って去ってしまうかもしれません。
そこで、「買うかか買わないか」の質問をせずに、
例えば相手が「セダンが好きです」と答えてくれれば、そのあとセダンの話を続けやすくなります。なぜセダンが好きで、セダンのどの点が好きで、買いたいのに買えない障害は何か‥相手の好みや状況をより深く探ることができるので、有利に営業を進めることができるでしょう。相手がスポーツカーと答えた場合も同様です。
加えて、二者択一の質問なので、「どちらが好きか」を顧客に考えさせることができます。顧客は自分の口から「セダンが好き」と言っているので、自分の発言に責任を持ちたい気持ちが起き、購買につながりやすくなるのです。これを一貫性の法則といいます。
デートに誘うにも「二者択一話法」は使える。
この理論は、なんと意中の相手をデートに誘い出すことにも使えます。
気になる異性をデートに誘う際に「デートしましょう」と誘えば、答えは「行く」か「行かない」の二択なので難しいですね。デートと言われると「え?デート?口説く気?私はそんなつもりないのに」と相手も身構えてしまいます。相手からすると乗りにくいでしょう。
では、こう聞かれたらどうでしょうか?
これならただの日常会話に聞こえるので、相手も返事をしやすいですね。
もちろん、「イタリアンが好き」と返されたら「じゃあ美味しいお店を知っているので今度そこに行きましょう」と続ければOK。相手も「イタリアンが好き」と答えてしまっている以上、自己決定の法則が効いてしまうので断りにくくなります。
「和食が好き」と言われたら、「じゃあ美味しい料亭に招待しますよ!」と言えばOK。相手がどちらの選択肢を選ぼうともデートに行くことができる、美味しい戦略なのです。
日程を決める時も、「いつにしますか?」なんて聞き方をしてはいけません。
宿題をしない子どもにも
この法則は応用性が高く、勉強をしない子どもにも使えます。
勉強をしない子どもに「勉強しなさい!」と命令口調で言えば「うるさいな!」と返されるでしょう。これは心理的リアクタンスが働くためです。
関連記事:強制されると断りたくなるのは「心理的リアクタンス」のせい
ではどうするかというと、「勉強しなさい」と命令するのではなく、選択の質問を投げるのです。
たとえば、
こうすれば、反抗される可能性は下がりますし、一度答えてしまえば「自己決定の法則」から、自分でやろうという意識が生まれるので、自分で勉強する可能性は高くなります。
二者択一話法 まとめ
二者択一話法は、うまく使うと「上手に人を動かす」ことができる話法です。
なかなか動いてくれない人を動かしたいときや、誰かを誘い出したいときに、ぜひ有効活用してください。
■関連記事
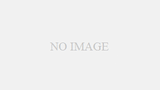



コメント